外食先で料理を残してしまったとき、
と悩んだことはありませんか?
特にガストのようなファミリーレストランでは、店舗ごとに対応が異なることもあり、
ルールが曖昧に感じられることがあります。
本記事では、ガストでの食べ残しをスマートに持ち帰る方法をわかりやすく解説。
容器の種類や料金、注意点に加え、環境への取り組みや他チェーンとの比較まで、
知っておきたい情報を網羅しています。
ガストでの食べ残し持ち帰りの方法とは?

持ち帰り可能な料理とそのメリットを理解する
ガストでは一部の料理について、食べきれなかった分を持ち帰ることが可能です。
対象となる料理には、
- パスタ類
- ハンバーグ
- ライス
- オムライス
- 唐揚げ
- 焼きそば
- グリル系メニュー
などが含まれており、
比較的水分が少なく再加熱しても味が変わりにくいものが選ばれる傾向にあります。
これにより、食事の満足度を損なうことなく、家庭での再利用にもつなげることができます。
食べ残しを翌日の昼食や夕食に活用することで、
外食の価値を最大限に引き出すことができるというメリットもあります。
また、節約や時間の有効活用の観点からも、
外食の残りをうまく持ち帰ることは非常に合理的な選択肢といえるでしょう。
特に一人暮らしや共働き家庭にとっては、食事準備の手間を減らせる点でも便利です。
持ち帰り容器の種類と利用方法
持ち帰りには専用の容器が必要となり、店舗によっては複数のサイズや形状が用意されています。
これらの容器は、主にプラスチック製で密閉性のあるものが多く、
汁気の多い料理にも対応可能な仕様となっています。
利用の際は、スタッフに申し出ることで対応してもらえるほか、
タブレット注文の際に「持ち帰り容器」の項目を追加オーダーすることでスムーズに手配できます。
サイズや形状は料理の内容に応じてスタッフが判断する場合が多く、
店内での案内表示や音声アナウンスによって利用を促す店舗もあります。
容器の使用後は、家庭で再利用したり、地域のルールに従って分別廃棄することも重要です。
ガストの持ち帰り政策について
すかいらーくグループ全体として、食品廃棄削減の観点から持ち帰りに積極的な姿勢を見せており、店舗では衛生面のガイドラインを守ったうえでの持ち帰りを認めています。
これは企業としての社会的責任の一環でもあり、
無駄を出さない飲食スタイルの普及を目指す取り組みでもあります。
なお、持ち帰り対応はすべてのメニューが対象というわけではなく、
- 生もの(例:サラダの一部や刺身風の冷菜)
- 冷製スイーツ(例:アイス系デザートやゼリー類)
などは、保存性や再提供時の品質保持の観点から対象外とされています。
これらの制限は、品質維持や提供基準に基づいたものであり、
注文時にスタッフへ確認することでスムーズな対応が可能です。
持ち帰り容器の料金と2024年の最新情報
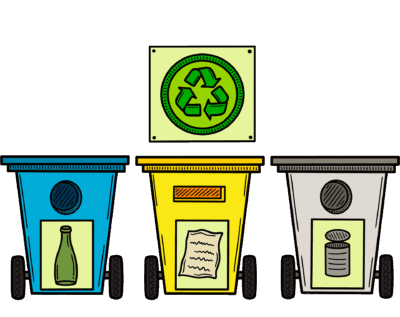
ガストの持ち帰り容器が有料になった理由
近年、地球環境への配慮が飲食業界でも強く求められるようになり、
使い捨てプラスチックの使用を減らす動きが加速しています。
ガストでは、こうした社会的背景を受けて、
2023年から持ち帰り用容器の無料提供を見直し、有料化を実施しました。
この変更により、環境負荷の軽減を目指すだけでなく、
必要な人だけが容器を購入することで資源の無駄遣いを抑える目的もあります。
また、これまで無料提供されていた容器にかかるコストも企業全体の経営課題となっていたため、
有料化によりその一部を利用者負担とすることで、より持続可能な運営体制を目指しています。
持ち帰り容器の料金早見表(2024年版)
- 小サイズ:約10円〜20円(主に小皿料理や副菜用)
- 中サイズ:約30円〜40円(ハンバーグやオムライスなどの単品用)
- 大サイズ:約50円〜60円(複数品目やボリュームのあるセット用)
※料金は地域や店舗の立地条件によって若干の差がある場合があります。
どこで購入できるのか? ガストの店舗情報
持ち帰り容器は、注文時に店内設置のタブレット端末から「テイクアウト容器」項目を選択することで簡単に追加できます。
また、注文後にスタッフへ直接依頼することも可能です。
初めて利用する方は、注文前にスタッフに確認をとっておくと安心です。
特に混雑時などは、事前の確認と申告がスムーズな対応につながります。
食べ残しを持ち帰る際の注意ポイント

タブレット注文時の持ち帰り番号について
一部のガスト店舗では、注文タブレットに持ち帰り機能が搭載されており、
持ち帰りを希望する料理に対して専用の番号を付けて指定する形式が採用されています。
利用者は、注文完了画面やレシートでその番号を確認できる仕組みになっており、
食後にスタッフへ「○番の料理を持ち帰りたい」と伝えることでスムーズに対応してもらえます。
また、タブレットには持ち帰り容器の追加オプションも表示されるため、
忘れずに選択することが大切です。
万一番号が不明な場合に備えて、料理名と時間帯をメモしておくとより確実です。
食材による持ち帰りの適正判断
ガストで提供されるメニューの中でも、持ち帰りに適している料理とそうでないものがあります。
たとえば、揚げ物(唐揚げやポテト)やライス類は冷めても味の変化が比較的少なく、
持ち帰ってから再加熱してもおいしく食べられるため、適しているといえます。
一方で、グラタンやソースがたっぷりかかった料理、クリーム系の冷製デザートなどは、
時間が経つと見た目や風味に影響が出やすく、持ち帰りには不向きとされています。
これらの判断は、当日の気温や持ち帰りまでの時間なども加味して慎重に行いましょう。
食べ放題プランとの相性
食べ放題形式のプランやサービスについては、原則として持ち帰りはできません。
これは利用者全員が公平な条件で食事を楽しむためのルールであり、
料金体系にも関わる重要な要素となっています。
また、食べ放題では、一定時間内に好きなだけ料理を楽しめる代わりに、
その場で完食することが前提です。
食べ残しの持ち帰りを認めてしまうと、量の調整が難しくなったり、
無用なトラブルを引き起こす可能性があるため、店舗側としても明確に制限しています。
事前にメニューや注意書きを確認し、ルールを理解しておくことが求められます。
フードロス削減につながる持ち帰りの取り組み

ガストが目指す食品ロス削減の目標
ガストでは「食べられるものは残さない」という考え方を企業理念のひとつに掲げ、
日々の営業活動において食材の無駄を最小限に抑える工夫を続けています。
厨房では仕込みの最適化や食材管理の徹底が図られ、
メニュー設計も残さず食べきれるよう配慮されています。
また、店頭では客に対して「食べきれなかった場合は持ち帰りも可能です」といった案内を積極的に行うことで、利用者の行動変容を促しています。
持ち帰り制度は、その一環として導入され、誰でも気軽に活用できるよう工夫がなされています。
持ち帰り利用による環境への影響
持ち帰り制度を通じて食品を無駄にしない取り組みは、単なるコスト削減にとどまらず、
資源の有効活用やCO2排出削減といった環境保全の観点からも高く評価されています。
たとえば、焼いたハンバーグや炊き上げたご飯をそのまま廃棄せずに自宅で再利用できれば、
そのぶん調理時に消費された電力や水の無駄も防ぐことになります。
このように、1人ひとりの行動が環境への正の連鎖を生み出すきっかけになっているのです。
もったいない精神の重要性
日本では古くから「もったいない」という言葉が日常的に使われてきましたが、
近年ではその価値観が改めて注目されています。
ガストの持ち帰り制度は、まさにその精神を実生活で体現できる仕組みです。
たとえば、夕食で残った料理を翌朝温め直して食べることで、
食材を大切に使い切ることができます。
こうした取り組みは、子どもたちへの食育や、
持続可能な暮らし方のモデルとしても意義深いものです。
他のファミレスでの持ち帰り事情

バーミヤンや夢庵の持ち帰り方
同じすかいらーくグループに属するバーミヤンや夢庵でも、
ガストと同様に食べ残しを持ち帰ることが可能です。
たとえば、炒飯やラーメンの麺類など、スープを含まない料理が対象となるケースが多く、
テイクアウト用の専用容器が用意されていることもあります。
なお、容器の有無や料金、持ち帰りの可否は店舗によって細かく異なるため、
利用前に店舗スタッフへの確認が推奨されます。
また、一部のメニューや時間帯によっては対応できない場合もあるため、
事前に電話などで問い合わせておくとより確実です。
ステーキガストでの食べ残し持ち帰りの方法
ステーキガストでは、ステーキやハンバーグ、ライスといったボリュームのある料理に対し、
希望すれば持ち帰り用の専用容器を提供してもらえます。
ただし、サラダバーやスープバーのような共有設備を利用するメニューは、
提供体制や運用上の都合により持ち帰り不可となることが多く、注意が必要です。
また、店舗によっては容器の種類や大きさが限定されているため、
料理内容に合わせて使い分けることが求められます。
持ち帰り容器の違いと料金比較
ファミリーレストラン各社が提供する持ち帰り用容器は、
素材やサイズ、機能性においてさまざまな違いがあります。
たとえば、バーミヤンでは主に軽量なプラスチック容器を使用し、
断熱性は低いがコストが抑えられているのが特徴です。
一方で、ステーキガストでは耐熱性の高い素材や仕切り付きの容器が用いられるケースもあり、
料理の保存性が高くなります。
料金は
- 小サイズで10〜30円
- 中〜大サイズで40〜70円
程度が相場となっており、利用シーンに合わせて選択することが重要です。
まとめ

成功する持ち帰りの秘訣総まとめ
- 容器を事前に注文しておくことで、スムーズに持ち帰りが可能になります。
- ソースが多すぎたり、水分量の多い料理はこぼれやすいため、避けたほうが安心です。
- 再加熱できるメニューを選べば、自宅でおいしく食べ直すことができます。
- 店舗ごとのルールや方針にきちんと従うことで、トラブルを避けられます。
- 量が多いと感じたら、早めに持ち帰りの準備を意識することも大切です。
- 家に持ち帰った後の保存方法や食べるタイミングも、計画しておくと無駄なく活用できます。
次回の注文時に注意するポイント
注文時は、自分の食欲や体調に応じた量を把握しておくことが重要です。
残る可能性が高い場合は、最初から持ち帰りを前提とした料理を選ぶと賢明です。
タブレット注文では容器の有無をチェックし、
わからないことがあればスタッフに確認を取っておくことで、当日の対応がスムーズになります。


